
春うらら、死に際のアノタちゃんことレーベル代表・庭野です。さて久しぶりに紙媒体で便乗できそうな特集を見つけたので、勝手に私の選んだ2010年代の邦楽アルバム・ベスト17をここでレビューしてみたいと思います。レーベルのHPであると同時に代表のプライベートブログとしても機能するこのはてなブログをご愛顧いただいている皆様にはお馴染みの、偉そうに御大層な御託が並んだ記事でございますが、ちゃんと本誌も購入しましたので、さしずめ井筒監督の「こちとら自腹じゃい!」的な感覚で、あぁ、またアノタの人が何か言ってるなあくらいの感覚で斜め読みしていただければ幸いです。尚、本誌では投票数によってランク付され、各選者が30作品選出するという形式でしたが、私の場合さらに絞り込んで、今後聞けなくなると困る、くらいの作品を17枚(中途半端)ここにリリース年順に紹介させていただいております。後で思い出したり、思い直したものが出てくればまた補填させていただきます。
ゆらゆら帝国「空洞です」2010

2012年に今後グループの作品に発生する著作権を放棄すると宣言したサンガツのそれ以前の最後のオリジナルアルバムはゲストを加えたギター×2、ベース、ドラム×4という編成で制作された即興と作曲の間を、デレクベイリーとグレンブランカの間を行き来するような、そして楽器と楽器の間を何かが行き来するような空気や距離感さえも音響として楽曲の中に盛り込んだ一つの発見を有する大作だ。そこには緻密でいて幼稚な発想も行き交い、実験的でいてただの衝動ともとれるような音楽的感動が溶け合っている。私は後で聞いた口だが、この約50年前の作品で演奏者にエレクトリックギターと電子楽器・クラヴィオリンを含む「七人の奏者によるミクロコスモス」(黛敏郎作・1957)にとても近しい印象を持った。つまりは「六人編成のロックバンドによるミクロコスモス」ということだろうか。
奥田民生「OTRL」2010

砂原良徳「liminal」2011

刀根康尚「Musica Simulacra」2011

tomato star「GRAGE BAND CAMP」2012

tomatostar.bandcamp.com
私ならばこのタイトルを思い付いただけで舞い上がって有頂天になってしまいそうだが、私が重い腰を上げてレーベルを立ち上げる10年以上前から(最初のリリースがなんと1999年、個人的には私がレーベルを始める何年か前、あるラジオ番組のデモテープオーディションでその名を知った。彼は今でもその番組のオーディションコーナーの常連である。)Bandcampで自身の作品をリリースし続けているリアル孤高のアーティスト、トマトスター。まるで生活の一部でもあるかのようにハイペースでリリースされた膨大な作品の中でも私が心臓を深く抉られたアルバムがこれである。と言いながら今になってようやく購入したのでここに補足的にリストアップしたいと思う。何故だか今のうちに入手しておかないと後々聴けなくなるのではないかというあらぬ焦燥感に苛まされ、今回の購入に至る。タイトルに負けず内容もシニカルで軽やかなインストゥルメンタル作品。ガレージバンドに付属しているサンプルやプリセットのような音色をこれ見よがしに多用した一見ソフトのデモンストレーションのような構造だがその骨組みは明らかに異質でまるでトランプを積み上げたピラミッドの如く不安定な印象を受ける、実際のサウンドも細かいバイブレーションによって音が痙攣して聞こえる。良くも悪くもこの作家が持つアマチュアリズムのような精神が脱構築性を伴って結果的にセンスの塊として作品になったように感じる。これはエレクトロニカや電子音響シーンとは別の世界で生成された新たなグリッチサウンドだ。尚、この作品は2014年「SUPER GARAGE BAND CAMP」、2020年「ULTRA GARAGE BAND CAMP」と2度リモデルされている。
tomatostar.bandcamp.com
tomatostar.bandcamp.com
池田亮司「supercodex」2013
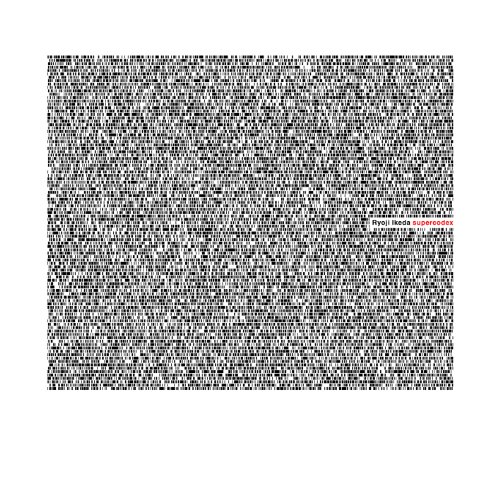
www.youtube.com
電気グルーヴ「人間と動物」2013

CMにも起用されたアルバムのリードシングル「Shamefule」。約4分の曲で歌われる歌詞はこれだけである。言葉を追っているだけでにやけてしまう珍妙さは一体どこからこみ上げるのだろう。昨今の韻を踏むが良し、世の中に不平不満をぶつけていれば良しとされる日本語ラッパーたちのリリックも是非同じように音を取り払って鑑賞してみてほしい。
本誌ではランクインどころか1票も見当たらなかったが見落としただけだと思いたい。カバーアルバムだからという点では小西康晴や民謡クルセイダーズが入っているし、何か他の理由で除外されたのだろうか。その辺りの事情を知らないから何とも言えないが、もし単純に誰の選出からも漏れてしまっただけだったしたら、よくぞこれをリストアップしていたと褒めて欲しいくらいだ。こういうものが抜け落ちるからいつの頃からか某誌はただの参考書になってしまった(被害妄想の激しい選者の誰かさんも補助くらいに思えと書いている)。制作ペース旺盛な矢野氏の他のテン年代アルバムももちろん必聴であるが、それにも増して、やはりピアノの弾き語りでオリジナルを凌駕するカバー演奏、加えて忌野清志郎の後期の作品を広くコンパイルしたという意義や「500マイル」「多摩蘭坂」でミニマムなアレンジを施した松本淳一の仕事もコンセプチュアルな意味合いを高めているように思う。そう、あえて全編弾き語りにしなかったことで何故かこのアルバムのコンセプトが明確化していることが特筆すべき点だ。意外にも全曲一人のアーティストのカバーアルバムというのもこれが初めてのようだ。ゼロ年代の超絶コラボユニット"yanokami"、テン年代の今作、そして既に次の年代(ニテン年代?)の重要作として新ユニット"やのとあがつま"による「Asteroid and Butterfly」が挙がっている。
このアルバムのプロトタイプとも言えるEP「post punk」、「Clampdown」は素材音もしくは曲を構成する具体音が辛うじて断片的に残された、もしくは施されたバージョンで発表された。この時期の彼が編み出した手法はハーシュともグリッチとも違う何らかのグルーヴを内包した超高速電子音を操る演奏法であり、あくまでその音が主旋律であると私は解釈しているが、それをわかりやすく伝えるためにこの2枚のEPを先行してリリースしたのではないだろうか。素材となったリズムマシンの音やサンプルボイスは逆転的に装飾音のようにあしらわれてそれをすり抜けるどころか衝突も恐れずに突き進む電子ノイズがまるで完璧な均整をもつガラスの破片のように飛沫化して乱反射し全く新しいハーモニィを作り上げる。そしてもはやshotahirama的としかいえない彼独自の電子音のみで構成されたアルバムが今作である。当初は配信のみでのリリースであったが徐々にこの先進的なサウンドにフォロワーが集まり翌年には近作をまとめたCDボックスセットの発売に至る。
坂本慎太郎「ナマで踊ろう」2014

まるで破滅を傍観するようなメタ・キャッチコピー。思えば、トラットリア作品の帯文もどれもユニークで秀逸だった。やがて小山田、坂本両氏のコラボレーションが実現したことは言うまでもない。因みにその際に中原昌也のポストを引き継ぐデス渋谷系の筆頭候補はお察しの通りshotahiramaである。
椎名林檎「日出処」2014

ということで未来のキャバレー建設計画を目論む菊地成孔率いる大所帯バンドによる活動再開後の二作目であり2021年現在、4月に解散することが決定してるからこれが最後のオリジナルアルバムということになった。私のような中途半端な教養ではこのバンドのポリリズムや高尚なテーマ性などを理解しきれないのが実情であるが、ただそれらはあくまでバンド内の共有言語でしかなく、リスナーに共用しようとしているのはもっと単純なグルーブだ。作り手気質と高慢が祟ってか私は長くこのグループの本質に気づくことができなかったわけだが、そんな個人的な見解はともかく再開後のサウンドを決定付けたとも言えるBABY METALのバックバンドのメンバーとしても名高い超絶テクニシャンである大村孝佳のギターはおそらく、再開後のライブにゲスト参加した元JUDY&MARYのギタリストTAKUYAの存在が影響しているかとも想像できるが、彼のアンサンブルを理解しないままアドリブで掻き毟るようなプレイからは1段階も2段階も踏み込んでおり、例えばキーボードと掛け合う難解なユニゾンプレイなどがこのアルバムでは見事に融和している。そしてそもそもこのバンド結成のきっかけはジャズのフュージョン・クロスオーバー初期の名曲である菊地雅章のCircle/Lineをカバーすることに端を発しているということから、菊池氏の70年代~80年代のデジタルに飲み込まれゆく低迷期ジャズへの2015年時点での最高水準の回答とも言える。ちなみに再開後の曲単位で言うと1曲目の「Ronald Reagan」と前作「Second Report from Iron Moutain USA」のマイルスデイビスのカバー曲"Duran"が出色だ。
本誌ではコーネリアスの久しぶりの新作が上位にあるが、私はその90年代を代表する作家たちが集ったこのグループのアルバムを重要視したい。元々は高橋幸宏のソロライブのために集められたバックバンドにこの名前を冠していたが高橋自身もメンバーとなって6人編成となった。中でもその重要性を高めたのはこの大仰なコラボレーションをバックに堂々と歌声を響かせたLEO今井の存在だろう。YMOと90年代アーティストの接続は既に円熟期を迎えていたがそこに新鮮な風を送り込んだのは間違いなく今井氏の声である。小山田の変拍子や幸宏氏のドラミング、砂原の図太いシンセサウンドにも負けない強靭なリズム感と声量、言葉の壁も超えてそのスキルを見事に活かし切ったLEO今井が爆発した作品である。同時に幸宏氏の前プロジェクトPUPAでは課題となったゼロ年以降のエレクトロニカとの乖離もこちらでは解消している。何よりも砂原氏がシンセベースを楽しそうに弾いているMVを観ると涙が溢れてくるのは私だけだろうか。
坂本龍一「async」2017

民謡クルセイダーズ「エコーズオブジャパン」2017

www.youtube.com
余談だがあなたはこのメンバー紹介動画を見てお気づきになるだろうか、錚々たるメンバーの中の斎藤ネコの存在に。そう、この大所帯プロジェクト(バンマスの仙波氏は白衣、メンバーはナースとパジャマで統一するというコンセプチャルな佇まい)は彼を経由して椎名林檎「Ringo EXPO 08」へ結実しているのである!
投票制によってランク付けした本誌ではこれが1位だったが、なるほど御誌らしい。個人的には前年の民謡クルセイダーズから折坂氏の登場まで中村とうようの血がどこかで再び沸点に達していたのだろうかと想像もしてしまう。当時も私は彼のポップス文化について書いた本などを読み返していたため一入その風潮に煽られたと記憶している。彼の歌唱法は一つの発明ではないかとさえ考える。様々なルーツを内包した新しいワールドミュージックが、とうようが言うところの混血音楽がここでまた生まれたのだろうか。本作は前作や他のEPよりもその度合いが強いが、その寛容性が音楽をまた軽やかにしている。
不理解を超える理解。2014年に独自の電子ノイズを携えてポストエレクトロニカ的なムーブメントを引き起こした後、再び既存のビート、特にダブビートを取り入れた作品シリーズなどを発表したshotahiramaがテン年代を経て辿り着いたのはオールドスクールなヒップホップを今あえて掘り起こし、そのマテリアルを一種のノイズとして制御してしまったようなクリックホップ(こう形容すればある意味Mo'Waxをはじめとするトリップホップをも巻き込む)とも言うべきトラック集で、さしずめブレイクビーツの標本採集のような、とても大勢の前でダンスを誘導するためのビートとは思えない偏執的な妖気も漂う代物で、何よりも数年前に完成させた自身の確固たるスタイルを捨てて臨んでいることに驚愕し、また、まるでインストヒップホップを更に形骸化させてしまったようないわゆる音響のカラオケ化という形容はこの作品に対する理解を超えた領域で降って湧いたもので、私の新作シリーズもここから発想を得たものであることも告白しておこう。同時に元祖デス渋谷系アーティスト・中原昌也氏の変名ユニット"Hair Stylistics"のビートメイキングにも共鳴しそうであることから、ここでネオ・デス渋谷系筆頭という妄想が多少なりとも現実味を帯びたことも記しておこう。翌年に更にドープ化させた「Stay on the Light」をリリース。また今月には更にこの手法をライブレコーディングで1発録りした音源を集めたアルバムをリリース。
<後記>
現在の私の最大の研究対象となっているクロマニョンズの作品は恥ずかしながら完全なる後追いのため、まだリストに加えるべきかも判断できていないが、彼らがゼロ年代後半からモノラル録音を採用しているという点が非常に興味深くまた、リリースの基盤はあくまでアナログ盤であってCDはアナログ盤をスピーカーで鳴らしている音を録音しているという事実にも驚嘆し開いた口が塞がらないままの生活を余儀なくされていることもここに記しておこう。そして私の記憶が正しければ、御誌の2020年ベストアルバムの中にクロマニョンズの最新作「MUD SHAKES」が選出されていたことが、私が彼らの作品を聞き返すきっかけになったはずであることもここに記しておこう。そして少し渋谷系のくだりで話題になった中原昌也氏のテン年代の作品群については、まず膨大な音源数を網羅できていない、ある種の批評性を超越している、時代間隔も超越しているという理由で全て選外扱いとさせていただいた(そんなこと言い出したらメルツバウは?とかキリがなくなるので諸々割愛)。もっともここに挙げた作品はあくまでこの年代における重要度の高い作品というだけであって必聴作品は星の数ほどあるということも付け加えておこう。もう一つおまけに我々川越ニューサウンドの作品はほぼ全てテン年代の邦楽アルバムであるということもここに記しておいても差し支えないはずだ。なぜならこのブログは私のブログだからだ。




























